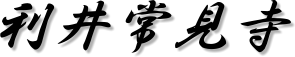住職法話1
| 今しかない! |
|---|
今年の7月22日のことです。覚えていますか? 46年ぶりの皆既日食に日本中が大いに沸きあがりました。 連日テレビでは特集が組まれ、日食メガネは店頭から売り切れ、 ある人は南国の島から、またある人は飛行機や船から、 一目でも日食を見ようと東奔西走しました。 部分日食の地域でも、日食の時間には多くの人が空を眺めたことでしょう。 さて、46年ぶりの日食と言う事で、滅多に見れない。 この時を逃しては!今しかない! そんな思いがあったのではないでしょうか。 しかし、親鸞聖人は「受け難きは人身、遇い難きは仏法なり」と仰られています。 これまで真実のみ教えに遇う事無く、煩悩を中心として、 迷いの六道を輪廻し続けて来た私たちにとって、 この娑婆に生まれ、お念仏のみ教えに出遇えた事こそが稀な事なのです。 46年ぶりどころではありません。 永き生死流転の末、今ようやく出遇えた仏縁なのです。 そんな遇い難き仏法に遇うご縁を頂きながら、そのみ教えを聞かずに過ごしては、大変です。 再び悪道へと堕ち、流転を繰り返すばかりなのです。 明日とも知れぬ命の私たちにとって、仏法を聞くのは今しかないのです。 お念仏のみ教えを聞くご縁を逃してはなりません。 今こそ後生の一大事をお聞かせ頂きましょう。 合掌 常見寺だより 平成21年10月号掲載 |
| 後世をしらざるを愚者とす |
|---|
最近、都心部において、「直葬」なるものが横行していると聞きます。 直葬とは、病院等で身内が亡くなりますと、そのまま火葬場に行くというものです。 お通夜も無ければ、葬儀も無いのです。 驚きを通り越して嘆かわしい限りです。 合理的であるとか、経済的であるとか、理由は様々なようですが、 生きている者の都合である事に変わりはありません。 何よりも、生きている事に価値があって、死んだら無価値と、 用済みのゴミを燃やして捨てるようなあり方は、命の尊さを知らない愚かな行為と言わねばなりません。 死に対して「死んだら終い」「どうせ死んだら無になる」というのは、 何の根拠も無い自己都合の考えに他なりません。 単に死ぬ事など考えたくないから、見て見ぬ振りをしているに過ぎないのです。 仏さまは因果の道理を説き、命の営みとは、花の種(因)が、 水や日光のはたらき(縁)を得て、花(果)を咲かせ、花が枯れれては、また種(因)となるように、 因→縁→果→因→縁→…と繰り返されるものであると示されるのです。 種の形が滅して、芽となり、芽の形が滅しては花となる。 姿かたちは変っても、種も芽も花も同じ命である事に変わりはないのです。 私たち人間もこの因果の道理に従っているのです。 この身が滅した時が命の終わりではないのです。 今、その事を知らずに、「死んだら無になる」「今さえ良ければ」と 煩悩を満たす事に終始する生き方は、必ず地獄・餓鬼・畜生のいずれかの悪道に堕ちるのです。 まさに「後世をしらざる愚者」の在り方なのです。 「後世を知る」とは、因果の道理を聞き受け、今の生き方を知ると言う事です。 煩悩に振り回されて地獄に向かう生き方は誤った在り方で、 真に正しい仏さまのみ教えを聞き受けて、浄土へ生まれ、 仏とならせて頂く事こそ尊い命の在り方と知る事なのです。 葬儀を自己都合で簡略するのではなく、亡き人を偲び、 亡き人の命を敬い、亡き人の命を通じて、自身の命の 在り方を知らせて頂く、尊い仏縁として頂きたいものです。 仏法など無くても生きていけると「後世をしらざる愚者」とならず、 仏法によって後世を知り、今を知る。 尊いみ教えによって尊い命の在り方をお聞かせ頂きましょう。 合掌 常見寺だより 平成21年7月号掲載 「後世をしらざるを愚者とす」(蓮如上人『ご文章』八万法蔵章より) |
| 学仏大悲心 |
|---|
明治十五年、常見寺第十八世住職の利井明朗、弟の鮮妙は富田本照寺の日野澤依氏と協力して、 本照寺境内に私立「行信教校」を設立されました。 その後、明治十九年に常見寺境内に移築され、その記念として三條實美公御染筆の「学仏大悲心」を賜り、 今も講堂の正面に掲げられています。   上の写真はその当時の行信教校の写真です。 本校舎の外観はそれほど変わらないようですが、周りの風景は想像も出来ないほどの変貌を遂げています。 もちろん、周りの風景だけでなく、社会情勢や生活スタイルなども、 今とは全く異なっています。娑婆の万事は諸行無常なのです。 唯一変わらないものと言えば、仏法しかありません。 そして変わらぬ仏法とは、阿弥陀さまの大悲のお心なのです。 この私を念仏申す者へとお育て下さった親心。 必ず往生せしめ仏と成らせると誓われた親心。 煩悩中心の私を、仏を仰ぐ者へとお育て下さった親心。 今、私たちがお念仏する事も、お念仏申そうと思う心の起こるのも、 みな阿弥陀さまの深いお慈悲にお育て頂いたおかげだったのです。 「学仏大悲心」はその親心を知らせて頂く事です。知ることは聞く事。 お聖教から、ご法話から、私をお育て下さっている阿弥陀さまのお心をお聴聞させて頂きましょう。 行信教校が創立以来、伝え続けてきた事、それは「学仏大悲心」より他には無いのです。 合掌 常見寺だより 平成21年3月号掲載 |
| 重箱のたとえ |
|---|
昔、「おせちもいいけど、カレーもね」ってCMがありました。 お正月にはどこのお店もお休みで、おせち料理を食べるのが主流だった頃ならではのCMです。 最近では、お正月早々から飲食店もデパートも開いていますから、 わざわざ「おせち」を作るご家庭も減ってきているのではないでしょうか。 そんな事を考えていますと、おせちを入れる重箱を見た事がない人が、 これから出てくるのかと思い、常見寺伝来「重箱のたとえ」を改めて味わわせて頂きたくなりました。 あるお正月の事です。新年の挨拶に来客があるので、 祖父が父に向かって「お重(重箱)は座敷に運んでおいてくれ」と頼んだのです。 父は言われた通り、三段のお重を持ち上げ、座敷に行こうとした時、 「ナンマンダー、ナンマンダー」と背後からお念仏が聞こえてきたのです。祖父の声でした。 振り返り父は「そんなに有難がらんでも、お重ぐらい運ぶで」と照れながら言うと、 「お前に言ったんとちゃうぞ」っと一喝。 それから祖父は「お前はそのお重のどこに手を掛けてるんや」と尋ねたのです。 父は「そりゃあ、全部持って行けって言うから、一番底に手を掛けてるわ」と応えると、 祖父は「そやろ、それが阿弥陀さんの救いの姿や。 一番上が上品の者、二番目が中品の者、三番目が罪悪深重の下品の者や。 途中に手を掛けたら救われん者が出てくるやろ。 全部救おうと思ったら、一番底に手を掛けなあかんやろ。それが阿弥陀さんや。 わしら罪悪深重の凡夫を一番の目当てにして下さったから、 十方衆生みな救われるんや」と…。 「重箱のたとえ」何度お聞かせ頂いても有難い事です。 しかし、私たちは本当に一番底だと思っているのでしょうか。 つい、「あの人よりはまし」「地獄や餓鬼よりは上」と思ってはいないでしょうか。 その思いこそが思い上がりの心です。 菩薩のような善人は仏さまのみ教えに素直に従い、地獄・餓鬼・畜生の者は、 その境界が苦しいが故に、救いを求め仏さまのみ教えをに従うのです。 ところが… 私たち凡夫は思い上がりの心から、自分をたよりにして、 仏さまのお救いの手を払いのけて生きているのです。 これが煩悩中心の凡夫のありさまです。 仏さまにとって、仏法を聞かない凡夫こそが一番救い難い者で、 この者こそ救わねばならないと、大悲のお心をもって、私たちを一番の目当てにして下さったのです。 阿弥陀さまの大悲のお心を、今年もお聴聞させて頂きましょう。 合掌 常見寺だより 平成21年1月号掲載 |
| 暑いときには寒いのが好きで、寒くなったら暑いのが好き。 |
|---|
今年のお盆参りの事です。あるご門徒さんのおばあちゃんに、 「今年の夏も暑いですね。おばあちゃんは暑いのと寒いのとどちらが好きですか」と尋ねたところ、 「暑いときには寒いのが好きで、寒くなったら暑いのが好きです」って。 思わず笑いそうになったのですが、次の一言に絶句でした。 「どちらも煩悩でっしゃろ」 何気ないその一言に目から鱗でした。そうなんです。 私たちはむさぼり(貪欲)や怒り腹立ち(瞋恚)のような激しいものばかりを煩悩と思いがちですが、 自分の都合に合わせて、好き嫌いを分別していく事こそ、根本的な煩悩のありようなのです。 煩悩については、私も法話で何度もお話をさせて頂きながら、 自分自身が煩悩を当たり前にしていた事に気付かされたのです。 まさに煩悩は具足しているのです。この身から決して離れる事が出来ないのです。 阿弥陀さまは私たちに、煩悩を煩悩と知らずに当たり前にしてはならない。 そしてこの煩悩こそが自らを苦しめる根源であると知らせて下さっているのです。 そんな煩悩具足の凡夫である私を、必ず救うとお誓い下さった阿弥陀仏のご本願。 私たちははかり知れないほどのご恩を頂いているのです。 もうすぐ報恩講。お念仏のみ教えを聞く者にとって、最も大切な法要です。 阿弥陀さまのご恩を知り、親鸞聖人のご恩をお聞かせ頂きましょう。 合掌 常見寺だより 平成20年10月号掲載 |
| 煩悩具足と信知して |
|---|
キュイーーーン!歯科医院に入ると診察室から聞こえてくる。 鳥肌が立つほど恐ろしい音。出来れば聞きたくないものです。 とは言え、聞かざるを得ない状況になってしまいました。 そう。虫歯になったのです。 診察用の椅子に座り、大きく口を開け、先生が覗き込む。 案の定、左下にポッカリ穴が開いてました。 先生が一応レントゲンを撮りましょうと言うので、撮影をすると上の歯にも虫歯を発見! 自覚も無ければ、先生が眼で見ても判らなかったのですが、 レントゲンにはきっちりと写ってたのです。 自覚がないのが一番厄介です。治療しようとも思わないのですから。 煩悩についてはどうでしょう。お経には私たち衆生の事を「煩悩具足の凡夫」と知らせています。 それは私たちが煩悩を離れられず、常に煩悩を中心に生きているにも拘らず、 その自覚もないまま、他人も、そして自分自身をも苦しめ、さらには三悪道(地獄・餓鬼・畜生)へと向かい、 苦界を流転し続ける身であると、私のありさまを知らせて下さっているのです。 如来さまからの診断結果は「煩悩具足の凡夫」、 治療方針は「本願力(阿弥陀さまのおはたらき)におまかせしなさい」、 特効薬は「南無阿弥陀仏」です。 自覚症状が無いからと、放っておいたら苦界に沈むばかりです。 虫歯なら歯医者にまかせれば良い。生死の事は阿弥陀さまにおまかせするより他にはありません。 我が身のありさまと、阿弥陀さまのおはたらきを しっかりとお聴聞させて頂き、お念仏の日々を過ごさせて頂きましょう。 合掌 煩悩具足と信知して 本願力に乗ずれば すなはち穢身すてはてて 法性常楽証せしむ (高僧和讃 善導讃) 常見寺だより 平成20年7月号掲載 |
| 地獄は一定すみかぞし |
|---|
「嘘をついたら閻魔さんに舌を抜かれるぞ!」 「悪さばっかりしてたら地獄に堕ちるぞ!!」 小さい頃にはよく言われたものです。その上、地獄絵図なんかを見せられた日には、 夜も眠れないほど怖かったものです。 最近ではどうでしょう。 「死んでから先の事よりも、今が楽しければ…、今の方が大事…」と後生の事を考えもせず、 自己の煩悩を満たす事こそ、人生を生きる上で最も大切だという方が増えているのではないでしょうか。 おそらく自分が「地獄へ堕ちるかもしれない」などとは微塵も思っていないはずです。 いや、真実のみ教えに出遇わねば、凡夫が自ら気付く事など出来ないのです。 『歎異抄』の第二条に宗祖が 「とても地獄は一定すみかぞし」(しょせん、地獄こそが定まった住み家である) と仰られています。 阿弥陀さまが必ず浄土に生まれさせるぞと疑いなく聞き受けたとき、 煩悩具足にして悪業ばかり、いかなる善行も及ばず地獄一定の身であったと知らされるのです。 如来大悲の目当ては、自らでは煩悩具足の身である事も、 地獄一定の身である事も知らぬ私であったのです。 鮮妙和上は「提灯の紋所」と言って、如来の真実に照らされて、闇が破られたなら、 そこには煩悩と書かれた紋所があらわれると仰られています。 宗祖の「地獄一定」のお言葉は、まさに往生間違いなし と信心の上から、わが身を知らされたお言葉であったのです。 この私を目当てとした、如来真実のみ教えをしっかりとお聴聞させて頂きましょう。 合掌 常見寺だより 平成20年3月号掲載 |
| お育てを味わう |
|---|
昨年、祖父、利井興弘の十七回忌を勤め、いろいろ祖父の事を思い出していました。 祖父の興弘と言えば、「食」に詳しく、自宅でカレーを作れば、香辛料を合わせて作る本格的な印度カレーでした。 大変辛い上に、食べていると月桂樹の葉が出てきたり、コリアンダーが出てきたり…。 本当はお子様カレーが食べたかったのですが…。 今から思えば、スパイスの香り立つ辛いカレー。あれが祖父の味だったんでしょう。 そんな事を思い出しながら、ふと気付かされた事がありました。 それは私の息子にお箸の持ち方を教えていた時のことです。 どこに力を入れたらいいのか、自分はどんな風に持っているだろうかと、あれこれ考えながら、 息子に教えていたのですが、息子は上手く持てずにすぐにスプーンに持ち替えてしまう始末。 もちろん一回で上手く持てるとも思ってはいませんから、次の日も、また次の日も、 繰り返し繰り返し教えていたのです。 その時、私は大事な事に気付かされたのです。 自分がお箸を持てる事は自然に身についた事で、大人だから持てるのが当然、 当たり前くらいにしか思っていなかったのですが、 私にも同じように繰り返し繰り返し教えてくれた人がいたのです。 そう、ウチで一番「食」に厳しい祖父が教えてくれていたのです。 そしてその事に気付かされた時、他力念仏のみ教えを味わうご縁を頂きました。全てがお育てだったのです。 小さい頃からお念仏に慣れ親しみ、本堂にお参りすれば、みんなと一緒にお念仏する。経本を開けば、 そこに「南無阿弥陀仏」とあるからお念仏する。 お念仏するという事を考えるとき、称えようという自分の意志で、自分の口を使って、 お念仏しているのだと思うなら、そこには、ただ自分のはからいだけがあって、 「おかげさま」という気持ちは全くありません。 どこまでも体を動かしている私を主体として見ているのです。 時には、ふっと口についた無意識の念仏のみが他力の念仏で、 自分が称えようと思う念仏は自力ではないかと言う方がおられます。 しかし、お念仏しようと思い立つ心が私の内に起ったのはなぜでしょう。 私と言う者は、元々お念仏をするような者なのでしょうか。 口を開けば愚癡ばかり、自分の欲を中心に据えて、好きな物は欲し、嫌いな物は排除しようとする。 ましてや、それが煩悩を中心とした愚かで苦しみに向う生き方とも知らず。 ただ煩悩を満たす事に終始し、お念仏を称えようとも思わないのが私の本性ではないでしょか。 そのような私が、こうして今、お念仏しているのは、この娑婆に生まれる前から、 繰り返し繰り返し阿弥陀さまのお育てを受け続けてきたからこそなのです。 お箸が上手く持てずに、お箸を投げ捨てスプーンを持とうとする子供のように、 阿弥陀さまのお育てを受けても、それに背を向け、楽な方へとばかり向う私を、見捨てる事なく、 ずっとお育て下さったおかげなのです。 ようやく阿弥陀さまのみ教えを素直に聞かせて頂き、お念仏するような者となったのです。 私が称えようと思って称えるお念仏。その思い立つ心は、阿弥陀さまのお育てのおかげなのです。 他力のお念仏とは、阿弥陀さまを主体としたお念仏なのです。 私が称えようと思ったから自力というのではなく、そこにこだわるのが自力のはからいなのです。 称えようと思い立つ心をも、遠く娑婆に生まれる前から、阿弥陀さまがお育て下さり、 「南無阿弥陀仏」のお名号となって私のもとではたらいて下さっているのが他力のお念仏なのです。 たまたま行信を獲ば、遠く宿縁を慶べ。(『教行信証』総序) 親鸞聖人も仰っておられます。 合掌 本願寺新報2007(平成19)年4月20日号掲載 |
| お花とおろうそく |
|---|
昨年末の事です。夕食時に坊守が不思議そうに私に尋ねるのです。 「お墓のお花はどうしてこちらに向けてお供えをするの?」 私は今さら何を聞くのかと思いましたが、よくよく聞いてみると、 昼間、自坊の裏手にあるお墓に行って見ると、お花がお墓の方へ向けてお供えされてたそうです。 しかもそれが一つや二つではないと言うから驚きです。 今までそのような事はなかったものですから、坊守も聞きただしたのでしょう。 その原因のタネを先に明かしておけば、 テレビでお墓の方に向けるのが正しいと放送された影響だという事がわかりました。 昨今、テレビの影響は大きく、健康番組などでも○○が体に良いと放送されれば、 翌日のスーパーでは品切れになるほど、 医療系の番組でもお医者さんの言葉より有名司会者の方を信じたり…。 ましてや宗教に関する情報は、お彼岸やお盆、お墓やお焼香など、 他宗派にも共通して用いられる用語ですから、 あたかもそれが仏教全般、全宗派に共通している作法であるかのように錯覚を起こしてしまいます。 他宗派と同じ用語だからといって、その教義や内容、作法は異なるのですから、 テレビ等の情報に惑わされず、正しい浄土真宗の仏事作法を行って頂きたいものです。 さて、話が逸れましたが、それではなぜ真宗では、お花を私たちの方へ向けるのでしょうか? まずお花は浄土の荘厳(お飾り)の一つです。 私たちの願望を仏さまに叶えてもらう為のものでもなければ、ご先祖の追善供養の為のものでもありません。 阿弥陀さまの浄土のすがたとして、美しいお花をお供えするのです。 そしてそれは単に飾りというだけでなく、阿弥陀さまからそのお花をもってご教化を頂いているのです。 つまり、どんなに美しい花も枯れ散っていく姿を私たちに見せ無常の理を示されているのです。 私たちはお花を供え浄土の荘厳をさせて頂きながら、その浄土の美しいすがたから浄土を欣慕すると共に、 一切の無常なる事を知らされるのです。 阿弥陀さまからのご教化ですから、私の方を向けてお供えをするのです。 中には汚れるからといって造花を使う方もいるようですが、 それでは阿弥陀さまのご教化にもなりませんし、何より自分の都合でしかありません。 お花は生花を用い、とげや毒のある花は用いないようにしましょう。 蛇足ではありますが、無常を知らせる為だからと、枯れるまで置いておかず、枯れる前に取り替えましょう。 ちなみに、お花の話が出ましたので、ろうそくについても一言いえば、真宗では電球のろうそくは用いません。 それはろうそくも世の無常なる事を私たちにご教化頂いているお荘厳の一つだからです。 よくろうそくの火を命に喩える事がありますが、その時、どこを見ますか?残りの長さでしょうか? この喩えは、どんなに残りの長さが長くても、風が吹けば消える命である事を示されるのです。 私たちは日常生活の中で、 「人間はいつか死ぬ」と思っていますが、いつかではなく、 いつ死ぬかわからぬ命と知らせているのです。 お花もろうそくも、阿弥陀さまからのご教化なのです。 その無常を知らされたならば、いつ死ぬかわからぬ命と知らされたならば、 後生の一大事の事は、今、聞かせて頂かなければならないのです。 また、お花とろうそくは、 美しい花は見る者に安らぎを与えるように、 生死の苦悩を除き、真実の安らぎを与えようとする阿弥陀さまのお慈悲の心をあらわし、 ろうそくの光は人生の灯となって私の生きる道を照らし、煩悩を焼き尽くす阿弥陀さまの智慧をあらわしています。 この智慧と慈悲が私のもとではたらいて下さっているのが 「南無阿弥陀仏」のお名号です。 浄土真宗でお花やろうそくは、阿弥陀仏のご教化の一つとして味わうのです。 そのご教化の中心を言えば、南無阿弥陀仏の名号なのです。 逆向きのお花のように私たちは様々な事に惑わされています。 真実のみ教えをしっかりとお聴聞させていただきましょう。 合掌 常見寺だより 平成21年1月号掲載 |
| あたたかなひかり |
|---|
陽の光が暖かくなってきました。冬の寒さに身を縮めていたのが嘘の様に、身も心も和らいできました。 暖かな光に包まれるとき、親鸞聖人のお書きになった御和讃を思い出すのです。 無碍光の利益より 威徳広大の信をえて かならず煩悩のこほりとけ すなわち菩提のみづとなる 高僧和讃の曇鸞讃には、阿弥陀様の他力信心を得たならば、 必ず煩悩の氷が解けて浄土を願う菩提心となると、 親鸞聖人は阿弥陀様のはたらきを讃歎されています。 この御文は私の煩悩が消えてなくなると言う事を言っているのではありません。 私たちは煩悩一つ除く事が出来ない身であり、この命が終わるまで煩悩を纏いながら生きなければなりません。 それはどうしようもない事実なのです。 しかしながら、阿弥陀様の光に出会い、 阿弥陀様の救いの目当てが煩悩具足のこの私であったと気付かせて頂くのです。 煩悩の火が燃える度に阿弥陀様のおはたらきを感じ、煩悩に振り回される度に慙愧するのです。 地獄行きの私の煩悩がそのまま喜びの種となるのです。 その阿弥陀様のはたらきが南無阿弥陀仏のお念仏となって私にはたらいているのです。 お念仏申すとき、春の光に包まれているような、阿弥陀様のお慈悲の深さを感じずにはおれません。 合掌 善巧寺寺報 第115号(平成17年4月1日)掲載 |